皆さんこんにちは!
クロスのリフォームをする前に、「クロスの張り替えって、いったい何をするの?」と、気になって、“クロス張り替えの作業工程を、あらかじめチェックしておこうかな”という方もいると思います。
そこでこの記事では、クロス張替えに必要な全ての工程を「養生→既存クロス剥がし→下地処理→糊付け→裁断→クロス貼り→ジョイント→見切り→清掃検査」の順で、現場で実際に何が起きるかを分かりやすく解説します。
期間や費用には触については、別記事のリンクを記載しますので、そちらでチェックしてみてください。
ここでは、記事を見やすくするために、「作業そのものの手順と品質チェック」だけに絞ります。
なお、クロス施工は作業中に粉じんや騒音は基本的に出ない作業です。
日本のクロス用の糊(のり)は臭いがほぼなく、有害性もほぼありません。
なので、「住みながらリフォームをする方」や「引っ越し前にリフォームをする方」でも、クロスの作業工程は同じになります。
ただ、住みながらの工事の場合だけ荷物移動がありますので、荷物移動の作業付きで作業工程をお伝えします。
引っ越し前にクロス工事をする方は、荷物移動だけ無しの想定でご覧ください。
良い仕上がりの見方とNGの直し方まで具体例でお伝えします。
読み終える頃には、職人がどんな道具を使い、どこを見ているかが手に取るように分かります。
クロス施工にかかる期間について詳しくはこちら
↓↓↓
【クロス張替え期間】6畳・1LDK・3LDKは何日?住みながらの工期と流れ
クロス施工にかかる費用についてはこちら
↓↓↓
㎡単価は当てにならない?クロス張替え費用の真実|6畳・1LDK・3LDKで解説!

もくじ
養生と準備:家具移動・動線設計・器具外しで“汚さない・壊さない”を徹底
最初に丁寧な準備をするほど、仕上がりは安定します。
どこを触れてよいか、どこは避けたいかを一緒に確認し、作業ルートを明確にします。
家具・床・建具の保護と、通路の確保、器具類の一時取り外しを順に進めるのが基本です。 「現場が整っていること」自体が、職人の手元の精度を押し上げます。
家具・家電の退避と通路養生|在宅施工の安全動線を作る
まずは大物家具を壁から60〜80cm離して作業スペースをつくります。
引き出しや棚の中身は箱にまとめ、家具と同じ名前の付箋を貼ると復旧の時に迷いません。
搬入出のルートにはノンスリップ系のシートを敷き、角部にはコーナーガードを当てます。
開口部は人の往来が多いので、扉の開閉範囲をテープで見える化すると接触事故を防げます。
通れる幅、置く位置、触れない物を最初に決めておくと、声かけの回数が減り、全体の段取りがスムーズになります。
集合住宅の共用廊下やエレベーター養生が必要な場合は、こちら→マンションのクロス張替えが高くなる理由7選【養生・在宅/空室など追加費用ガイド】も参考になります。
床・建具の養生材の使い分け|マスカー/ノンスリップシート/養生テープ
養生費は、見積もりに加算されます。
予算を抑えたい方は、業者に「ある程度でいいよ。」と、声掛けをしておきましょう。
床はクッション性のあるシートを面で敷き、その上に薄いボードを重ねると局所荷重にも強くなります。

巾木・ドア枠・窓枠はマスカーで広範囲を覆い、角はテープで“逃がし”を作ると剥がし跡が出にくくなります。 テープは弱粘着を選び、木部や塗装面では試し貼りをしてから本貼りに移りましょう。
ドアや引き戸の可動部には切り欠きを入れ、可動時に養生が突っ張らないよう調整します。
最後に、作業の流れに沿って養生の“継ぎ目”が段差にならないかを手でなぞって確認すると、後工程での引っ掛かりを防げます。

コンセント・照明・カーテンレールの取り外し手順と復旧の注意
スイッチ・コンセントはプレートを外し、ビスと一緒に小袋へ保管します。
器具本体や電気配線に触れる作業は専門資格の範囲があるため、必要時は有資格の職人を手配します。
照明はカバーや傘のみ外し、ソケット部を保護したうえで作業します。
カーテンレールは、クロスを張るとビス穴の位置が分からなくなるので、レールを外したら、ビスだけ緩め(ゆるめ)に戻しておきます。
復旧時はプレートの平行と締め付けの均一を意識し、周囲のクロスを巻き込まないよう軽く押さえながらネジを締めると仕上がりがきれいです。



既存クロスの剥がし:下地を傷めない剥離のコツと残糊・紙残りの処理
クロス剥がしは“ただ外す作業”ではありません。
ここで下地を守れたかどうかが、後工程のパテ量と仕上がりのフラットさを左右します。
私はいつも、壁の状態を一緒に確認しながら進めます。
不安なところは声をかけて、手を止めて、納得のいくやり方で続けましょう。
特殊下地(砂壁など)は手順が変わるため、詳しくは内部記→砂壁はそのまま貼れない!クロス張替え前に知るべき【実際の施工手順】をご覧ください。
剥がし道具の選択と当て方|地ベラ・スクレーパー・スチーマー
最初に目立たない位置で“めくれやすさ”を試します。
表層と裏紙の二層に分かれるタイプは、表層だけを手でめくり、裏紙は水分を入れてからスクレーパーで薄く削ぐのが基本です。
地ベラは“刃物のガイド”です。
刃先が下地に当たらない角度を保ち、力は前ではなく横に逃がします。
スチーマーや霧吹きで湿らせる場合も、含ませすぎると石膏ボードの紙が膨らむので、湿らせて待つ→軽く削ぐ→また少量含ませる、の小刻み運転が安全です。
メーカーの施工要領でも、**下地を切らない・濡らし過ぎない**が鉄則です。
参考:サンゲツ
↓↓↓
①一般ビニル壁紙 施工要領書
②リリカラ 施工要領書

石膏ボードを傷めないコツ|目地・ビス頭・角部の扱い
目地やビス頭は段差になりやすい“弱点”です。
剥がし中に紙がささくれたら、無理に引っ張らず、刃を寝かせて“なで切り”で止血します。
入隅・出隅は、まず角から**外側に**向かってめくると、角の紙を切りにくくなります。
欠けが出た場合は、その場で小さなパテで仮押さえしておくと、後の本パテが決まりやすいです。
もし剥がしで下地の状態に不安が出たら、広げずに一度全体を確認し、必要なら下地補修の段取りに切り替えます。

下地処理(パテ・研磨・シーラー):仕上がりを決める“壁の凸凹平滑化”
新しいクロスの見え方は、下地の整え方でほぼ決まります。
気になる段差やヒビを先に消しておくと、貼ったあとに「うっすら筋が見える」といった残念さを防げます。
私はいつも、壁の表情を一つひとつの壁ごとに確認しながら作業を進めます。
気になる点があればその場で職人と共有します。
クラック・目地スジの処理順序|段差の“消し方”の基本
細いヒビや石膏ボードの継ぎ目は、そのままクロスを張ってしまうと筋が透けやすい場所です。
まずヒビの上をうっすらV字に開くようにカッターを走らせ、弱い部分を取り除きます。
次に下地テープ(メッシュ等)をまっすぐ貼り、パテで包み込みます。
一度で盛り切ろうとせず、
広めに薄く伸ばして周囲へなだらかにつなげるのがコツです。
角ベラや幅広ベラを使い分け、出っ張りは“押してならす”、凹みは“足してならす”の繰り返しで段差を消します。
斜めからライトを当てて陰影を見ると、残りやすい“段差の尾”に気づけます。
平滑になった手応えを指先で確かめつつ、必要に応じて次工程へ進みます。



パテ3回塗りと研磨の勘所|番手選びと粉だまり対策
パテは「下塗り→中塗り→仕上げ」の三段階が基本です。
下塗りは欠けや凹みを埋める目的で、必要以上に広げません。
中塗りで周囲へ面を広げ、境目を分からなく(平滑に)します。
仕上げではヘラ跡を消すイメージで極薄に整えます。
研磨は粗い番手から入り、仕上げに細かい番手でならす順番です。
研いだあとは手のひらで面をなで、引っ掛かりがないかを確認します。
研磨粉の取り残しは後の密着に響くため、刷毛やウエスで丁寧に取り除き、角や巾木上の“たまり”も見落とさないようにしましょう。



シーラー塗布の目的と適量|吸い込みムラを抑える
パテ面と既存下地では、糊の吸い込み量が違います。 この差を整えるのがシーラーの役割です。
ローラーや刷毛で薄く均一にのばし、たまりやすい角部は先に刷毛で切っておくとムラが出にくくなります。
塗りすぎは表面に膜を作り、逆に密着を弱めることがあるため、“薄く・均一に”が基本です。
塗布後は表面のべたつきが収まり、触れても粉が移らない状態になってから次に進みます。
ここまでの丁寧さが、仕上がったときのフラットさと継ぎ目の落ち着きにそのまま表れます。
糊付け・裁断・貼り込み:糊(のり)で貼る
クロス貼りは“段取り七割、手元三割”。
ここでは、糊の扱い・裁断の精度・壁面での圧着という三つの要所を、迷いなく進められる順にまとめます。
道具や材料は同じでも、手順の整え方で仕上がりは大きく変わります。
いま壁の前に立っているつもりで、一緒に手順を重ねていきましょう。
糊の種類と粘度管理|オープンタイムと“のり負け”を防ぐ考え方
糊は“塗る”より“効かせる”意識が大切です。
塗布後に少し時間を置く(オープンタイム)ことで、クロスと下地のなじみが安定します。
目安は季節と現場環境で揺れますが、機械糊付け後は**折りジワを作らずに大きく畳み、上積みしない**、これだけでムラが減ります。



寒い時期は効きが遅く、急ぐと後伸びのふくれを招きがちなので、作業速度より“糊の効き”を優先しましょう。
メーカー手順でも、オープンタイムの調整・上積み厳禁・貼付後の拭き残し防止が基本として明記されています。
裁断・柄合わせ・耳処理|“一手先”を読んでロスとズレを減らす
裁断は、貼る壁の“縦のクセ”を先に見るところから始めます。
天井と床の通り、開口の位置、下地の波。
これらを踏まえてカット寸法を決め、**余尺は最小限に**。
柄物は基準線を一本決め、必要なら墨出しやレーザーで通りを確保します。
ジョイント部は耳の厚みや印刷差で段差が出やすいため、**耳落とし/重ね切り**のどちらで行くかを事前に統一します。
重ね切りを選ぶ場合は、**下敷きテープを入れて下地を傷めない**のが鉄則です。

国内メーカーの施工要領にも、下地を切らない配慮や有効巾での施工推奨が示されています。
貼り込みの順番と圧着|天井際・出隅・入隅の基本動作
クロス貼りは“上から順に、真っ直ぐ”が基本です。
天井際は上端を軽く合わせ、地ベラをガイドに**押さえる→余分を逃がす→刃を寝かせて切る**。出隅は折り癖を付けてから**表面側をやさしく押さえ**、角に糊を効かせるイメージでローラーを当てます。
入隅は“突っ込み過ぎず、逃し過ぎず”。
片側を先に決め、もう片側は**1〜2mmの逃げ**を残してストレスを抜くと後の開きが出にくくなります。
最後に全面をスムーサーで“十字・斜め”に転がし、**ジョイント・角・巾木上**をローラーで丁寧に追いかけます。 メーカー手順でも、角部の押さえ方や圧着・清拭の徹底が推奨されています。

ジョイント処理・見切り納め・清掃検査:継ぎ目を消し、仕上げを固める
最後は、ぱっと見の印象を決める大事な仕上げです。 ここが整うと、同じ材料でも“ワンランク上”に見えます。
私はいつも、遠目と近目の両方で確かめながら、継ぎ目の表情やキワの直線、拭き取り跡まで丁寧に整えます。
一緒に確認ポイントを共有し、気になるところはその場で微調整していきましょう。
重ね切りと開先処理|ジョイントを目立たせない切り方
継ぎ目は“切る前の準備”で差が出ます。
まず上下の通りを合わせ、重ね代を一定にとってから、**下敷きテープ**を差し込みます。
刃は寝かせて軽く引き、**一度で切り離そうとせず**二〜三回で層を落とすと下地を傷めにくいです。



切り離し後は端材を抜き、スムーサーで空気を追い出してからジョイントローラーで軽く転がします。
それでも線が出るときは、**開先(ほんのわずかに開いて押し込む)**で糊の逃げ道を作ると段差が落ち着きます。

光が強い窓際やダウンライト直下は影が出やすいので、斜めからも見て、筋が見えない位置まで整えましょう。
「ここ、もう一息」が仕上がりの満足度を押し上げます。
巾木・廻り縁・窓枠の納め方|カッター角度と地ベラの当て方
見切りは“切る向き・当てる場所・力の抜き方”を揃えると、一直線に決まります。
地ベラは**面に沿わせてガイド**にし、刃は**気持ち寝かせて**素材に沿って滑らせます。
巾木は上端の“返し”にクロスを軽く送り込み、**押さえる→余分を逃がす→切る**の順で無理なく納めます。
廻り縁や窓枠の角は、先に**角落としの下切り**を入れてから本切りすると、カドのめくれが出にくいです。
ゴムパッキンや塗装面は刃が入りすぎないよう、小刻みにストロークを刻みます。
切り粉や糊のにじみはすぐに拭き取り、黒ずみの原因を残さないことが大切です。
直線が通ると、部屋全体がきりっと整って見えます。
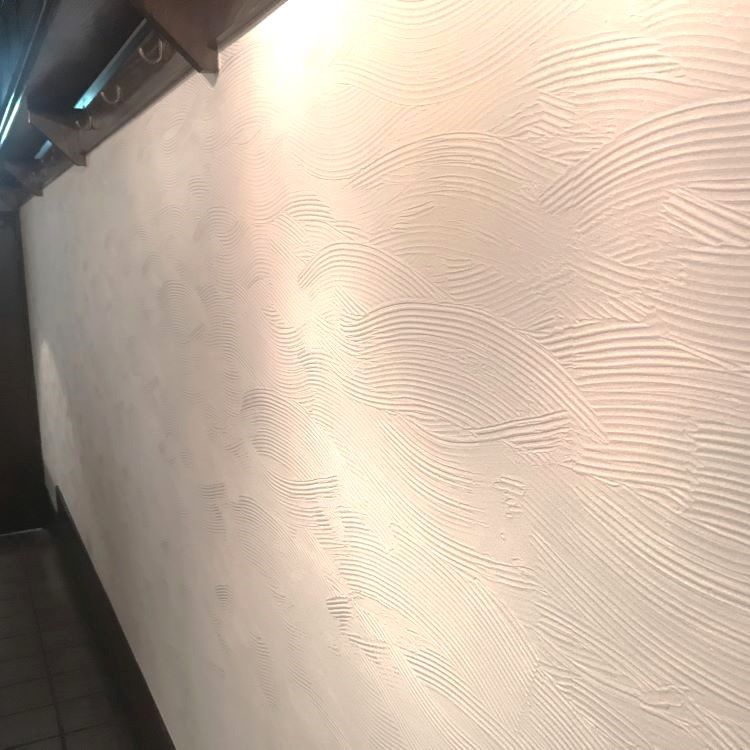
仕上げ清掃と最終検査チェック|糊ダレ・浮き・シワ・角の浮き
仕上げは“見え方の最終確認”です。
まず、**ジョイントの線・出隅と入隅・巾木上の直線**を遠目から確認し、近づいて糊の拭き残しや毛羽立ちを点検します。
次に、手でなでて**浮きやシワの手触り**を探り、気になる箇所はローラーで再圧着します。
窓際や照明直下は影が強いので、斜めからも見て繊細な筋を拾いましょう。
拭き上げは乾いたウエスで仕上げ、角の押さえ跡や端材の取り逃しがないかを再確認します。
もし下地の点状の変色やカビの兆候を見つけたら、再発防止の処置が必要になることがあります。
その場合は別記事の→【クロス張替え】カビで費用はいくら増す?防カビ・ボード交換・漏水修理のリアル相場こちらで対処の考え方を確認しておくと安心です。
まとめ
ここまでのクロスの張り替え工程は、養生の丁寧さが土台になり、その上に剥がし・下地・貼り・仕上げが積み上がる流れでした。
準備で動線と保護範囲を決めておくと、後の作業が落ち着き、仕上がりの精度が自然に上がります。
剥がしでは下地を守る意識が最優先で、残糊と紙残りを見分けながら“濡らしすぎない・切りすぎない”を徹底します。
下地処理はパテと研磨を段階的に行い、シーラーで吸い込み差を均してから、次の工程へ進むのが安全です。
貼りでは糊の効きと裁断の精度をそろえ、角や開口部で無理をさせないことで、全体が静かに整います。
仕上げはジョイントと見切りの直線を見極め、気になる点を一緒に微調整すれば、毎日目に入る場所が心地よく仕上がります。
工程ごとに「やる理由」を確認しながら進めることが、きれいさと満足度を両立させる近道です。
このように、クロスをキレイに仕上げるのにも時間をかける必要があります。
「クロス施工には何が必要なのか?」を知ることで、業者の話が分かるようになります。
クロスの仕上がりをよくするためにも、業者と一緒に無理のない作業工程を組んでください。

